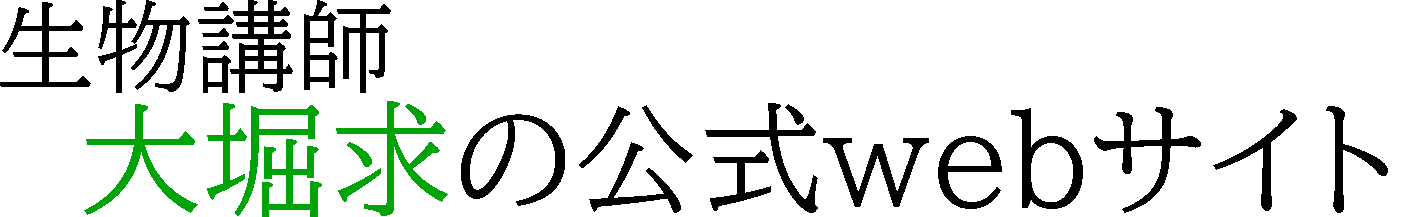今回は「坂口博士がどのようにしてノーベル賞受賞に至ったか」ですね?



そう。でね、今回から少し難しくなるので、ちょっと覚悟が必要だ。
といっても、生物受験生ならわかるはずだけどね。



はいっ、頑張ります!



まずね、免疫の研究は1900年代の初頭には始まっていて、さらにそのころにはすでに「免疫担当細胞は自己と非自己をどうやって見分けているのか?」が議論されていたんだよ。



「自己と非自己の識別」はそんなころから研究の対象になっていたんですね。



やがて、自分の免疫細胞が自分の細胞などを攻撃してしまう「自己免疫疾患」という現象が存在することが明らかになったんだ。



「自己と非自己の識別ができなくなってしまう」とうい現象が発見されたけわか・・・



そうなんだ。
やがて1960年代になると「免疫細胞は、最初にありとあらゆるものを攻撃するものが作られたあと、その中の『自分自身を攻撃するもの』が排除される」という考えが出てきた。



「自己免疫疾患」という現象から「自分を攻撃するという危なっかしいもの」も作られると考えたわけか…



そうそう。
さて、次の実験は1961年、ジャック・ミラー博士がおこなったものだ。ちなみに当時は胸腺のはたらきはわかっていなかったんだ。





胸腺がないと「免疫不全」になるんだから、胸腺は免疫に関する機能を持っているっていうのがわかりますね。それと、「リンパ球の種類が少ない」というんだから、ある種のリンパ球の誕生に関与しているのもわかりますね。



そうだね。
ここでミラー博士は、胸腺がないと誕生してこないリンパ球に
「T細胞」と命名したんだ。このTはthymus(=胸腺)の頭文字だ。



なるほど、Tは胸腺のことだったんだ。



そしてこの発見からけっこう後の1980年代の終わりころになって、胸腺はT細胞を生み出すだけでなく「自己応答性のものを排除する」ということも発見された。





なるほど、前回のコラムの内容につながるわけですね。



そして1990年代の終わりころには、その「自己応答性のT細胞の排除」はアポトーシスの誘導によることもわかった。



おお、だいぶ現代に近づいてきましたね。そろそろ坂口博士の登場ですね♪



そう。あともう少し。
ところで、前回のコラムでも話したけれど、この「自己応答性のT細胞の排除」は完ぺきではなく、一部の自己応答性のT細胞は生き残ってしまうことが明らかになった。



だからこそ自己免疫疾患が起こるんですよね。



そう。
ということは、この生き残ってしまった自己応答性のT細胞を排除するシステムも存在するはずだ。ここで注目されたのが「サプレッサーT細胞」だ。



サプレッサーT細胞? そんなのいましたっけ?



この細胞は1971年、多田富雄博士によって提唱されたもので、いろいろな研究から「他の免疫細胞のはたらきを抑制する(suppress)ようなT細胞がいるはずだ」という考えから提唱されたんだ。



なるほと、「抑制T細胞」か…



きっとこのサプレッサーT細胞が、生き残った自己応答性のT細胞を抑えているのだろうというと。で、多くの研究者がサプレッサーT細胞を探した。



で、見つけた・・・



いや、見つからなかったんだ。なので、1990年代の終わりころには研究者の間では「そんな細胞はいない」とされてしまった。



見つからなかったのなら説明しなくてもいいのでは?



いや、坂口博士の受賞の経緯説明には必要なんだよ。とにかく、時代は「他の免疫細胞を抑制するようなT細胞はいない」という雰囲気になっていた…ということを覚えておいてね。



わかりました。「そういう雰囲気になっていた」んですね。



一方、1969年、西塚泰章博士・坂倉照好博士は次の実験を行った。





あれ? 胸腺を除去したらT細胞が誕生しないんだから、「免疫系が活発化」とか「自己免疫疾患」とかありえないんじゃないですか?



だよえねえ。
そして、1982年、この西塚博士の研究室にやってきたのが坂口氏だ。



おお、ついに登場♪



坂口氏はさっきの実験に次の操作を追加してみた。つまり、胸腺を除去した後、同じ遺伝子型のマウスの成熟T細胞を注入してみたんだ。すると…





あれ? 正常になった。つまり、自己免疫疾患が起こらなくなったわけですね。



ということは、注入した成熟T細胞の中に自己免疫疾患を抑制するものが混ざっていたことになるね。で、坂口氏はそのようなT細胞を探すことにしたんだ。



で、見つかった、と…



はやい、はやい。もちろん見つけたんだけど、もう少し説明を続けよう。
T細胞にはヘルパーT細胞とキラーT細胞があるのは知っているね。
ではどう違うのかというと…





TCRなら知ってます。「T細胞受容体」ですよね。でも、CD4?
CD8?



そうだね、TCRはMHC分子に提示された抗原と結合する部分だね。で、CD4・CD8は次のように使うタンパク質だ。





ほほ~、MHC分子をしっかりつかむためのもの?



そうなんだ。
で、ここで大事なのは、細胞表面にCD4があるがのヘルパーT細胞、CD8があるのがキラーT細胞ということだ。



あっ、ということは、細胞表面にCD4とかCD8じゃないものを持つのを探せばいい?



そのとおり。それがきっと自己免疫疾患を抑制するT細胞だ。
で、探したんだけど…



またみつからなくて「やっぱり他の免疫細胞を抑制するT細胞はいない」となってしまった…



だったらノーベル賞もらえないでしょうが。
1995年に見つかったんだけど、10年もの歳月が費やされた。



お~、ずいぶんかかりましたね。
で、ヘルパーT、キラーTとどう違ったんですか?



その細胞はCD4と、さらにCD25も持っていたんだ。
坂口氏はこの細胞に「制御性T細胞」と命名した。



わ~、ついに出ました、制御性T細胞♪



ところがここからがまた大変だったんだよ。



えっ? だって見つかったんだからもうノーベル賞ですよね?



1990年代の終わりころはどんな時代だったっけ?



あっ、そうか、「他の免疫細胞を抑制するようなT細胞はいない」という雰囲気になっていたんでしたよね。



そうそう、それそれ。
なので他の研究者たちは・・・



「は~? 制御性T細胞? まゆつばだね」という感じ?



そのとおり。
なので、もっと決定的な証拠を突きつけなければならない。



もっと決定的?



そう、遺伝子レベルで「ほらっ、制御性T細胞の遺伝子があるでしょ」っと突きつけないといけない。



おお~、まだ道のりは遠そうですねえ。



さて、長くなってしまったのでつづきは次のコラムにしよう。次回は「遺伝子レベルでの証拠」を見つける話だよ。そして次々回のコラムでは制御性T細胞の発見によって今後の医療がどのように変わっていくかについて説明する予定だ。