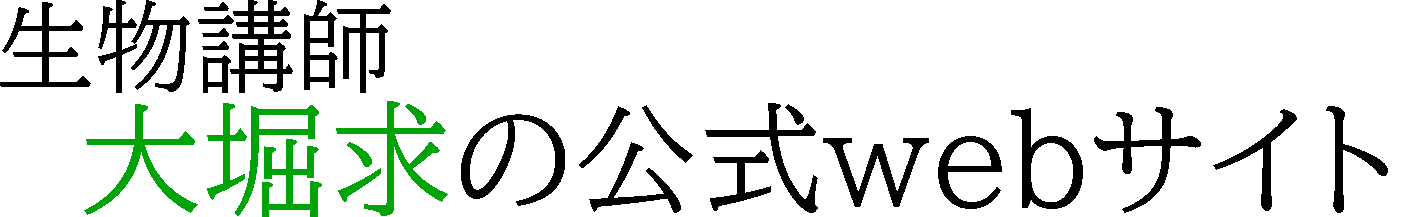やりましたね~、2025年のノーベル生理学・医学賞は日本人も受賞しましたねえ♪



そうだね。受賞の対象となったのは「末梢性免疫寛容と制御性T細胞」の研究成果で、坂口志文博士、そしてブランコウ博士・ラムズデール博士の3人がいっしょに受賞したね。



まっ、まっしょうせいめんえきかんよう? せいぎょせいてぃ~さいぼう?



では今回のコラムでは、末梢性免疫寛容と制御性T細胞について簡単に説明しよう。



お、お願いしまっす。



まずは白血球の復習ね。次の図を見てみよう。





あっ、これは生物基礎で習いますね。



だよね。
ところで「T細胞には自己と非自己を見分ける能力」があるんだ。



ええっ? どうやって見分けるんですか?



まず、胸腺という器官でいろいろなT細胞が誕生する。つまり、ありとあらゆるものを攻撃するT細胞たちが誕生してくる。で、その中には自己細胞・自己物質を攻撃してしまうものも混ざっている。こういうT細胞を自己応答性のT細胞っていうんだ。





自己細胞・自己物質を攻撃したら困りますよ~。



だよね。だから、胸腺では自己細胞・自己物質を攻撃するようなT細胞を排除する仕組みがあるんだよ。この仕組みを中枢性免疫寛容っていう。



なるほど、自己と非自己を見分けるというよりは、自己を攻撃するもの
がいなくなるというやり方なんですね。つまり、非自己を攻撃するものしかいなくなる。





ところで困ったことに、胸腺では自己を攻撃するT細胞を完全に排除できないんだよ。少数だけれど、すり抜けてしまうT細胞が存在する。



それは困りますね。



だから、きっとそうしたすり抜けてしまった自己応答性のT細胞を抑える役割を持ったものがいるはずだ…と坂口志文博士が考えて、そして探した。



で、見つけた…と、



そう、見つけた。この細胞はT細胞の一種で「制御性T細胞」と命名されたんだ。そして、「胸腺による自己応答性T細胞を排除するシステム」を中枢性免疫寛容といったね。これに対して、「胸腺をすり抜けてしまった自己応答性T細胞を制御性T細胞によって抑制するシステム」を末梢性免疫寛容というんだよ。



あ~、これで自分のT細胞に自己細胞・自己物質が攻撃されないで済みますね。



次回のコラムでは、制御性T細胞発見の経緯について、少し詳しく説明する予定だよ。さらに次々回のコラムでは制御性T細胞の発見によって今後の医療がどのように変わっていくかについて説明する予定だ。