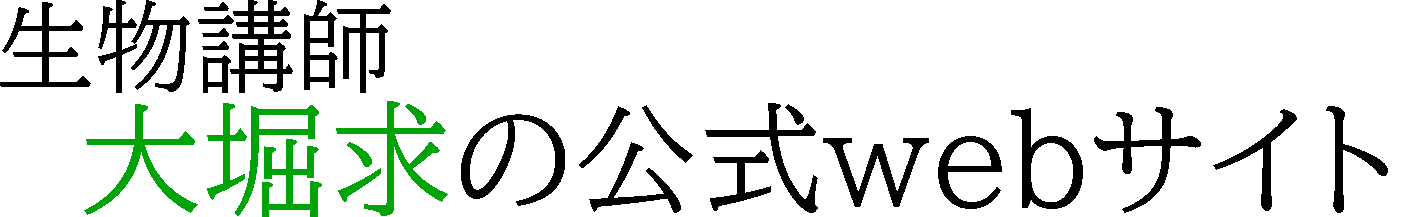下の図は言わずと知れた光合成曲線だね。





あっ、知ってますよ。光補償点・光飽和点・光合成速度・見かけの光合成速度・呼吸速度…





ではここで問題です。



き、来たな…



図が赤色光の場合の曲線だったとすると、緑色光の場合はどのように変化する?





か、考える問題ってやつですね…



そう。暗期じゃない。今この場で考えて答えを出すんだ。でも、ちょっとおまけして選択問題にしよう。次の①~⑥の中に正解が1つある。





う~ん…



ではヒント。
光合成でよく使われる光の色は?
逆にあんまり使われない光の色は?



ああっ、それなら習いました。
「光合成の作用スペクトル」
ってやつですよね。



そうそう、それそれ。下の図のように習ったはずだね。





ええ~っと、光合成は青い光と赤い光で効率よくおこなわれて、逆に緑色や黄色の光だとあまり効率よくおこなわれないんですよね。



ということは、図が赤色光でおこなっていたものとすると、緑色光にすると…?





①か④か⑤ですよね。



そう。半分消去できたね。
では①・④・⑤のうちのどれが正しいかを考えよう。
ここで必要なのは「光合成の作用スペクトル」の正しい
理解だ。
まず第1に、赤色光の場合と緑色光の場合で光合成速度が違うけれど、これは「同じ強さの赤色光と緑色光を用いて」比較しているとい
うことだ。



それは例えば「赤色光も緑色光も同じ
1万キロルクスで光合成をおこなわせた」
という感じですよね?



そのとおり。
例えば1万キロルクスの赤色光の場合の光合成速度は「10」、
同じく1万キロルクスの緑色光の場合の光合成速度は「5」、みた
いな感じだ。





そうか、ということは逆に、同じ光合成速度を得るには
赤色光よりも緑色光の方がより強い光が必要だということ
ですね?



おおっ、いい感じ!
例えば、同じ光合成速度「10」を得るには、
赤色光なら「20」の強さ、緑色光なら「30」
の強さが必要ということだ。





ということは④か⑤ですね♪



あとは、光が強くなると光合成速度は一定になるけれど、
この一定になったときの値が赤色光と緑色光で違うのかどうかだ。



そもそも、どうして一定になってしまうんだろう?



おっ、いい調子。「どうして?」はとても大事だ。
こんなふうに考えればわかりやすい。





二人三脚?



そう、二人三脚の速さで考えるんだよ。
例えばXさん・Yさんそれぞれの最高速度は10km/時・20km/時とすると、この二人三脚の最高速度はいくつ?



10km/時ですよね?



そうだよね。足が速いYさんはXさんに合わせるしかない。YさんがXさんより速く走ろうとすると転んでしまうからね。
これと同じ理屈なんだ。光合成は「光が強いほど速くなる反応」と
「温度や二酸化炭素濃度が高いほど速くなる反応」の2つからなる。
つまり、これら2つの反応の二人三脚の速さが光合成速度だ。





そうか、反応Xと反応Yで、
速い方が遅い方に合わせるわけですね?



そう。そうすると次のようになる。
仮に、現在の温度は20℃、二酸化炭素濃度は0.03%で、このときのYの最高速度は「20」ということにしておく。
光の強さが「0」のときは反応Xが走れないので、反応Yも走れない。なので二人三脚の速度(=光合成速度)は「0」。
光が強くなるにつれて反応Xが走りだし、それに合わせて反応Yも走り出す。つまり、光が強くなるにつれて二人三脚の速度(=光合成速度)も上がっていく。それが区間A。





でも光が強くなってくると反応Xがどんどん速くなっていきますよね。やがて反応Yの最高速度の「20」よりも速くなりますよね?



そう。反応Xは光が強くなれば「20」でも「30」でも速く走れるけれど、反応Yはそうはいかない。だから、今度は反応Xが反応Yに合わせることになる。それが区間Bだ。





なるほど。だから、光の強さが強くなると一定になるんですね。



では、一定になる高さを変えるにはどうしたらいい?





あっ、反応Yは温度や二酸化炭素濃度で
速さが変わるんだから、「温度」または
「二酸化炭素濃度」を変えれば、高さが
変わる?



すばらしい、そのとおりだ。
例えば温度を変えてやれば…





…という感じになる。



そうか、ということは、光の色を変えても
高さは変わらない。だから正解は⑤♪





お見事!!



「正しく理解する」ということがちょっとわかりました♪



この問題における「正しい理解」はまず「光合成の作用スペクトル」だ。縦軸の「光合成速度」は、いろいろな色の光を「同じ強さで」測定した場合のものだ。
そして・・・



そして、光合成曲線は光が強くなると「どうして一定になってしまうか」ですね。



そう。光合成は「光の強さで速さが変わる反応」と「温度・二酸化炭素濃度で速さが変わる反応」からなることが原因だったね。
そして最後は「一定になる高さはどうやったら変わるか?」ということだ。



これまではこういう問題が出たとき、ただ答えを暗記してました。



そういう勉強法が役に立たないのは入試問題を解いたときに分かるよね。単純な穴埋め暗記問題しか解けないからね。
それに、そんな暗記勉強法では生物がちっとも面白くないでしょう。
というわけで「生物の勉強法 第11話 「生命現象を正しく理解する(その1)」でした。大堀の参考書「大堀先生 高校生物をわかりやすく教えてください!(上下巻)」(学研)には、この「生命現象の正しい理解」の体得法が他にもいろいろ書いてあります。旧課程用ですが、新課程でも十分に使えます。そして代ゼミの1・2学期講座「ハイレベル生物」や夏期講習「大堀の正しく理解する生物」では、やはりこの「生命現象の正しい理解」をバンバン鍛えていきます。受講するぞ~という学生さんたち、楽しみにしていてくださいね♪