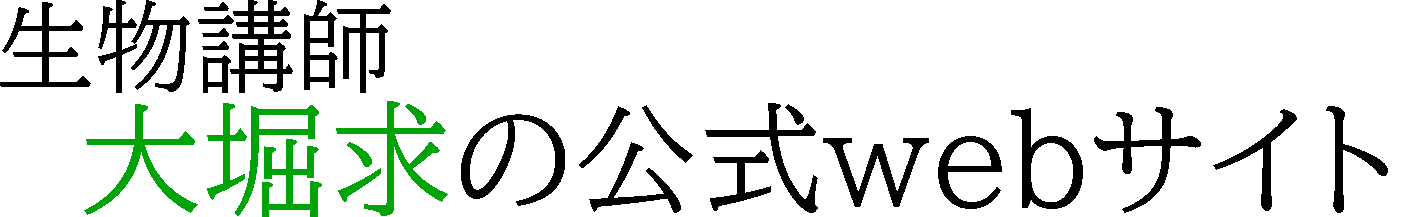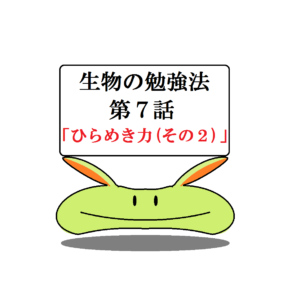さて今週の問題です。



ええ~、今日も?
お盆くらい休みましょうよ~。



受験生にお盆休みはありません。
インスリンは血糖濃度を下げるホルモンですが、飲んでも効くでしょうか?



な~んだ、そんなの簡単ですよ~。
インスリンはタンパク質。だから、飲んだら消化されてしまうので効きません!!



ですが~、ではここからが問題です。



へ? ここからが問題か・・・



糖質コルチコイドは血糖濃度を上げるホルモンですね。
では、このホルモンは飲んでも効くでしょうか?
つまり、糖質コルチコイドを飲んだら血糖濃度は
上がるでしょうか?



ええ~、そんなの習ったこと・・・あっ、そうか。この発想はダメだったっけ・・・。
インスリンは消化されちゃうから効かない。じゃあ糖質コルチコイドを飲むと消化されるのかなあ…



おっ、とってもいい思考過程だね。
じゃ、ヒント。糖質コルチコイドの成分は
なんだっけ?



ええ~っと、たしかステロイドでしたよね?



そのとおり。これは第2話で説明したよね。
で、このステロイドは消化されません。



な~んだ、じゃあ簡単。消化されないんだったら効きます!



う~ん、思考がもう一段階必要だ。
だって消化されなかったら、
消化管で吸収されないんじゃない?



あっそうか。消化されないと消化管で吸収されない。
ということはウンチと一緒に出て行っちゃう?



そうだね、そういう場合もある。
じゃあもう1つヒント。次の図は細胞膜の様子だ。
細胞膜はリン脂質と各種膜タンパク質からなっている…
というのは知っているね。





さて、受動輸送にはどんなタイプがあるか知っている?



えっ? 受動輸送のタイプ?
考えたこともなかったな…



受動輸送には次の図のように「リン脂質二重層をすり抜ける」「チャネルを通る」「担体による輸送」の3タイプがあるんだ。
ちなみに「ポンプ」が使われるのはすべて能動輸送だ。





CO2・O2、そして脂肪やステロイドなどの極性がない物質は、
リン脂質二重層の部分を高濃度側から低濃度側に勝手にすり抜けてしまうんだ。
そして、極性がある物質は脂溶性の部分を通過できないのでチャネルか担体によって輸送される。



極性がない物質?
ある物質?



簡単に言えば、極性がある物質とは「水に溶ける物質」
ということ。反対に極性がなければ「水に溶けない物質」
または「油に溶ける物質」だね。各種イオンやグルコース
・アミノ酸※は水に溶ける物質だ。



あっ、そういえば神経のところでナトリウムチャンネルとかカリウムチャネルって習いますね。



そうそう、各種イオンとH2O分子はチャネルをとおる。
そしてある程度大きくて水に溶ける分子、例えばグルコースやアミノ酸は担体によって輸送されるんだ。



はっ! ということは、ステロイドでできた糖質コルチコイドは
細胞膜を勝手に通過してしまいますね。



おっ、いい反応だ。
ということは、消化管の内表面を構成する細胞の細胞膜も・・・



通過してしまいますね。



ということは、ステロイドでできたホルモンは消化されない
けれど・・・



消化されないけれど吸収される!!



正解!!



ということは、糖質コルチコイドだけでなくステロイドでできたホルモンは飲んでも効きますね。



そのとおり。正解にたどり着いたね。
なんでも暗記で済ませようとせず、既に持っている知識を駆使して新しい知識を作り出す、それを・・・



ひらめき力という!!
というわけで「生物の勉強法 第8話 「ひらめき力を鍛えよう(その3)」でした。大堀の参考書「大堀先生 高校生物をわかりやすく教えてください!(上下巻)」(学研)には、この「ひらめき力」の体得法が他にも書いてあります。旧課程用ですが、新課程でも十分に使えます。そして代ゼミの夏期講習「大堀の正しく理解する生物」では、やはりこの「ひらめき力」をバンバン鍛えていきます。受講するぞ~という学生さんたち、楽しみにしていてくださいね♪
※アミノ酸にも極性がないもの(=水に溶けないもの=疎水性のもの)が存在する。